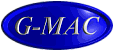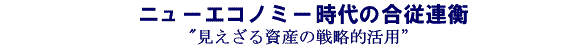|
| 13:00 | |
合従連衡に基づく日本企業の知的資産の再構築
yet2.com(米国) 創業者・社長 ベンジャミン・デュポン
氏
株式会社イェットツー・コム・アジア 取締役副社長 七條 良一
氏
-
合従連衡に基づく知的資産活用の世界的動向
- 日本企業に於ける知的資産活用の現状と課題
- インタンジブル・アセットとしての知的資産のM&A戦略上の意味
- 埋もれた知的資産の再活用による企業価値の最大化
概要:
|
1990年代末よりアメリカで始まった新たな知的資産活動はヨーロッパ・日本に広がりつつある。特にアメリカの先進企業では知的財産部だけではなくトップダウンによる全社的戦略・運動に変化してきている。企業は毎年巨額の研究開発費を投入しているが、そのうち一握りしか製品として日の目をみることはなく、多くは企業の保管所に眠っている。一方で多大の金額を特許維持費として支払い続けている。日本企業においてもこの埋もれた資産をどのように活用できるのか?そのためには何を変革しなければならないのか?また、その選択肢として合従連衡をどのように戦略的に構築して行くべきか?Yet2.comの創業者であり、デュポン家直系の御曹司であるベン・デュポン氏とプライスウオーターハウス、ベインアンドカンパニーにての合従連衡を含めた経営コンサルティング経験を踏まえ、P&G、デュポン、日立、NECなど多くのクライアントを抱えるyet2.comアジア地域責任者である七條氏より、特に日本企業の課題にフォーカスを当てお話頂く。 |
|
 |
| 13:45 | |
合従連衡に基づく知的資産戦略−新たなコア・コンピータンス−
ビジネスIPR 共同代表
東京大学工学部大学院非常勤講師 柴田 英寿 氏 - ニューエコノミー時代の知的価値とは?
- ニューエコノミーに対応できていない日本の企業経営
- 知的資産を梃にした合従連衡とは
- 戦略的知的資産ポートフォリオ・マネジメントとは?
概要:
|
技術開発系の企業にとって、知的財産権の管理が益々重要になっている。業界の次のテクノロジーとは何か?何処にその資源があり、現在それを生み出しているキー・プレイヤーはいるのか?自社開発をすべきか、それを買収するべきか?合併後特許資産をどのように再編成するか?競合他社が向かっている技術開発の方向は?非コア・テクノロジーをどのように梃入れし、“金のなる木”に変えるのか?柴田氏はNGOであるビジネスIPRの共同代表として週刊東洋経済で知的資産に関するコラムを連載し、「オフ・バランス経営革命」(東洋経済新報社)など当該分野に於けるオピニオンリーダーとして活動されている。 |
|
 |
| 14:30 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソンの合従連衡とライセンス戦略
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケア カンパニー 最高顧問 廣瀬 光雄
氏 -
合従連衡とプロダクト統合 -ポートフォリオの再構築-
- ライセンス戦略に基づく成長加速
- 新規ビジネスモデルの共有化
概要:
|
ジョンソン・エンド・ジョンソンが現在世界中で販売している使い捨てコンタクトレンズは、もともと北欧のベンチャー企業が立ち上げた事業であった。これはベンチャーの持つインタンジブルをそのグローバルなマーケティングの仕組みと融合されることで成功したモデルである。ブランド・マネジメントでも名高いジョンソン・エンド・ジョンソンの日本法人ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社の元代表取締役でビジョンケア・カンパニー最高顧問である廣瀬氏から話しを伺う。 |
|
 |
| 15:15 | |
アフタヌーン・ティーを取りながら歓談
|
 |
| 15:45 | |
インタンジブル資産としてのブランド−企業価値とIR
株式会社アイ・ビイ・アイ 代表取締役 トーマス R.ゼンゲージ
氏
-
企業価値拡大のためのブランド・マネジメントとは?
- 戦略的ブランドマネジメントとIR/コーポレートコミュニケーションズ
概要:
|
グローバルに合従連衡や企業編成が増加する今日のビジネス環境下において、IRとコーポレートコミュニケーションを通しブランドエクイティをどう企業価値に変換し、それをどう最大限に生かすか、ということが重要な経営課題となっている。 |
|
 |
| 16:30 | |
21世紀の戦略的デュー・デリジェンス
中央青山監査法人 トランザクション・サービス部
代表社員 三橋 優隆 氏
-
ニューエコノミー時代のデュー・デリジェンスとは?
- 特許及び知的財産権のデュー・デリジェンスの要諦(特許権の消滅・無効・専門性の継承など)
- ブランド価値の判断基準
概要:
|
ニューエコノミー時代のデューデリジェンスは、特許・知的資産・ブランドなどの見えない資産をどのように評価し、プライシングを行うかが重要となる。その評価は、合併後のパテント・ポートフォリオからブランドの変化まで視野に入れたものでなければならず、より専門性と経験が重要となる。三橋氏からは当該分野に於ける豊富な経験から21世紀に求められる戦略的デューデリジェンスについてお話を頂く。 |
|
 |
| 17:15 | |
議長閉会の辞
|